
医療情報企画部
大槻 彰 先生
| <特集>DICOMの過去・現在・未来 3.DICOMの未来〜将来の統合型システムにおけるDICOMの役割 将来の統合型システムにおけるDICOMの役割 |
 |
横河電機株式会社 医療情報企画部 大槻 彰 先生 |
| 9月25日に公表された厚生労働省の医療制度改革試案をはじめ、最近ではこれからの医療をめぐる話題が毎日のようにマスコミをにぎわしている。
その行方は、はっきりとはわからないものの、より良い医療を目指すためにIT(Information Technology)を活用した医療情報システムに寄せる
期待は大きいと感じている。 放射線部門を中心とする画像ネットワークに関して言えば、ここ数年のDICOMの発展と普及により、画像の保存や読影に関してはあるべき姿が 概ね明確になってきた。これからの情報システムは、ある限られた範囲の業務や機能を満たすだけではなく、まわりのシステムと連携したり 情報を共有化するなど、より高度な情報の統合が求められるようになっている。例えばPACSを例にとっても、画像を保存して読影環境を提供する という基本的な役割に加え、レポートへキー画像を提供する、参照用の画像を広く施設全体に供給する(或いは電子カルテに画像を提供する)、 遠隔画像診断に利用するというような広範囲の情報活用が求められるようになってきている。しかも、システムの連携を考えるたびに カスタムアプリケーションを作成するのは非常にコストがかかることから、標準的なサービスや通信インターフェースを持ったシステム、 別のベンダーの製品と組み合わせが可能なシステムが求められるようになってきている。 ところで、これから放射線部門を中心とした情報の統合はどのように進んで行くのであろうか。その方向性を確かめる上で非常に参考になるのが 日米欧で進められているIHEプロジェクトである。IHEは簡単に言うと病院全体のシステム統合のガイドラインを作成し、そのガイドラインに従った システムをマルチベンダーで構築して統合の有効性を実証するというプロジェクトである。IHEは標準規格自体を定めることを目的としているのでは なく、既に存在する標準規格の中から最適なものを選択し、その標準に従って構築する統合されたシステムの姿と具体的な方法を示すものである。 そのIHEが選択している標準規格がDICOMとHL7である。病院全体というとHISが中心にあると思い勝ちだが、現在のIHEプロジェクトの中心は 放射線部門なのである。放射線部門のシステム化の中心的規格はやはりDICOMである。本来IHEの目指すところは病院全体のシステム統合であるが、 まずは放射線部門を中心に検討を開始した背景には、DICOMの普及により放射線部門がいつの間にか最も標準化を進めやすい部門になっていた ということがあげられるだろう。 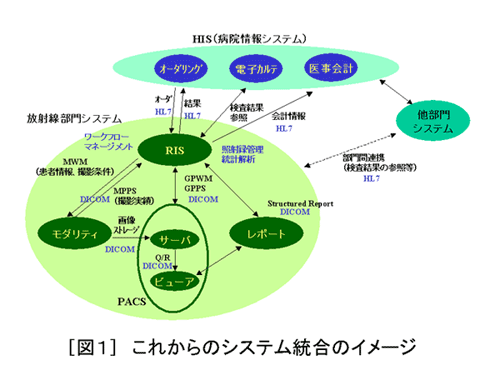 図1にIHEの考え方をベースとしてこれからの放射線部門を中心としたシステム統合のイメージを描いてみた。放射線技師、放射線医、受付等の
放射線スタッフの業務を円滑、かつ効率的に運用できるようにまとめるのがRISの役割である。RISはモダリティ、PACS、レポートといった要素を
統合する位置付けにある。また、RISは病院全体を統合する病院情報システム(HIS)とのインターフェースとしての役割をも受け持つ。
図1にIHEの考え方をベースとしてこれからの放射線部門を中心としたシステム統合のイメージを描いてみた。放射線技師、放射線医、受付等の
放射線スタッフの業務を円滑、かつ効率的に運用できるようにまとめるのがRISの役割である。RISはモダリティ、PACS、レポートといった要素を
統合する位置付けにある。また、RISは病院全体を統合する病院情報システム(HIS)とのインターフェースとしての役割をも受け持つ。ここでは、ざっとシステムの連携の様子を見てみる。まず臨床部門受付でHISを使って患者の本人確認、保険確認、来院目的の確認、 事前オーダの確認等がなされる。次に患者が診察室に入り、医師の診察を受け、医師はHISを使って画像の検査オーダを実施する。検査オーダは HISからRISへ送られる。この時に連携で使用されるのはHL7という標準規格である。 やがて患者が放射線部門の受付にやってくると、受付スタッフは検査オーダをRISの端末で確認することにより、スムースに受付業務をこなす ことができる。あらかじめオーダがわかっているので、検査時に必要な事前準備をすることもできる。また、会計に必要な情報をRISから医事会計 システムにリアルタイムに送ることが出来る。この時に使用される標準もHL7になるであろう。 検査室の端末では技師がHISからRISに送られてきたオーダにより、確定されたオーダから仕事を始めることができる。やがてやってくる患者の 本人確認を行う。同時に、DICOMのMWMサービスを利用してRISからオーダ情報(患者基本情報や撮影条件)がオンラインでモダリティへ送られるため、 入力の手間の軽減や入力ミスの低減が図られる。撮影が終了すると画像はDICOMのStorageサービスによりPACS(画像サーバ)へ送られるとともに、 撮影実績がDICOMのMPPSサービスによりRISへ送られる。MPPSの情報をもとに照射録が自動的に作成され、管理されることも期待されている。 読影医はモダリティからPACSへ送られてきた画像を順次読影することもできるが、通常はHISから送られてきた(読影)オーダにしたがって 読影して行く。オーダと実際に撮影された画像のリスト(実績)をつき合わせることにより検査の進捗を確認することができる。レポートはDICOM ビューアと連動して書くことができ、DICOM画像がもつPIXELデータ以外の付帯情報(撮影条件等)も自動的にレポートに取り込まれる。IHEでは レポートもDICOMのSR(Structured Report)サービスを使って書いたり参照したりすることを検討している。ただし、実用化されるまでには もう少し時間がかかるようで、当面は現在のようなベンダー独自のレポートを含めていろいろなレポートが使われることであろう。また、 HISや他の部門システムと連携することにより、読影時にいろいろな臨床データや臨床経過を参照することができる。 RISはオーダの進捗状況、すなわち画像検査が終了し、レポートが完成したことを把握し、HISへ通知する。 診療科の医師は画像を含む検査の進捗状況をHIS端末でオーダ別に確認することができ、画像やレポートを参照して診断を行う。 このように将来に放射線部門のシステムはHISとの連携を強化し、RISを中心として技師や医師、スタッフのワークフローをサポートする。 照射録管理や様々な統計情報の解析も可能となる。そのテクノロジーの中心がDICOMである。また、RISがHISとうまく連携するためにはHL7と DICOMの情報のマッピングが重要であり、RISのデータベースの設計にあたってはHL7を十分意識する必要がある。標準に準拠したシステ統合の 最大のメリットは、ユーザが仕様書を書けることであり、ユーザがそれぞれの用途に応じた最適な製品やシステムをマルチベンダーの中から 選択できることである。今後、JMCPを初め多くの場でIHE(日本での活動はIHE-Jと呼ばれる)のプレゼンテーションが行われると思われる。 機会があれば、是非そのような場に足をお運びいたたきたいと考える。 |